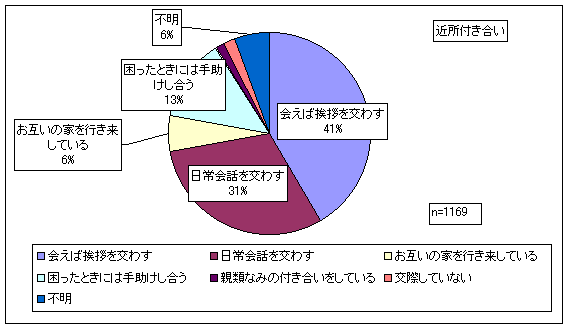結果
あなたは、普段隣近所とどのような近所付き合いをしていますか、という問に対して、調査の結果、「会えば挨拶を交わす」は41.7%、「日常会話を交わす」は30.6%、「困ったときには手助けし合う」は13.2%、「お互いの家を行き来している」は5.6%、「親類なみの付き合いをしている」は1.3%となり、「交際していない」と回答した人は2.1%になっている。
考察
この結果から、ほとんどの人が近所との付き合いはしているが「会えば挨拶を交わす」、「日常会話を交わす」といった比較的浅い付き合いをしている人が多いようである。特にこの傾向は年齢では20代の人、居住年数では5年未満の人に顕著に現れている。20代の人と居住年数が5年未満の人は「交際していない」も他と比べて多くなっている。一方、比較的深い付き合いをしている人は、対象地区でみると農業地区と佐貫地区が他の地区と比べて多く、居住年数が「20年以上」と「生まれた時からずっと住んでいる」も多くなっている。これは居住年数が長いと近所の人との付き合いが増えるためと考えられる。それと性別でみると女性の方が多く、年齢でみると40代が多い。これは専業主婦の人で近所の人とふれあうことが多く、子どもがいて共通の話題があるためと考えられる。この近所付き合いが地域への参加状況とも関連してくると考えられる。
6-2.地域行事や活動への参加状況
結果
あなたは、地域の行事や活動にどの程度参加していますか、過去1年に参加した経験のある活動を全てあげてもらったところ、「地域のまつり」(4割弱)と「町内会・自治会活動」(3割弱)が多くなり、以下「PTA活動」(2割弱)、「スポーツ・文化サークル活動」(2割弱)、「地域あるいは地区の運動会」(1割強)と続いている。何かしら地域行事や活動に参加している人は約7割になっている。特にニュータウン地区は地域の活動に参加している人の割合は高く、活動状況をみるとPTA活動や子供会活動など子供を介した活動への参加割合が高い。しかし、年齢でみると20代の人の約5割、居住年数では5年未満の人は約4割の人が「どの活動にも参加したことがない」と回答している。
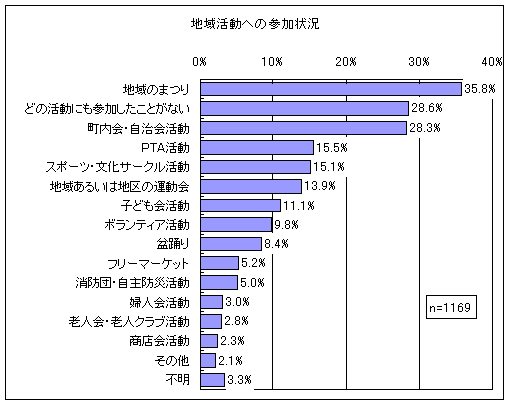
考察
以上から、若い人は参加の意欲が低く、居住年数では5年以上の人はそれほど大差ないので、5年未満の人はまだ地域に馴染めていない為と考えられる。これに対してニュータウンの人が参加状況が良いのは、子供のいる年代が多く、子供を介しての活動が多いためであると思われる。
この2つの問をみると、若い人と居住年数が短い人が近所付き合いは薄くまだ地域に馴染めていない為か、地域への参加状況が良くない。一方で、ニュータウンの人は近所付き合いは浅いが、地域活動への参加状況は良い。また女性は、男性に比べ近所付き合いも深く、地域行事や地域活動への参加状況も良い。
6-3.地域福祉を高めるために必要な施策
結果
「地域福祉を高める為には何が必要ですか」という設問に対し「学校教育の中で福祉教育を推進する」が4割強、第2位が「やさしい街づくりを推進する」で4割弱、第3位が「高齢者の生きがい対策の推進」、「在宅福祉サービスを充実する」がともに3割となっている。その他、「社会教育の中で福祉教育を推進」が3割弱、「ボランティアの養成や活動の推進」「経済援助を推進」「社会福祉施設づくりを推進する」がいずれも2割強となっている。
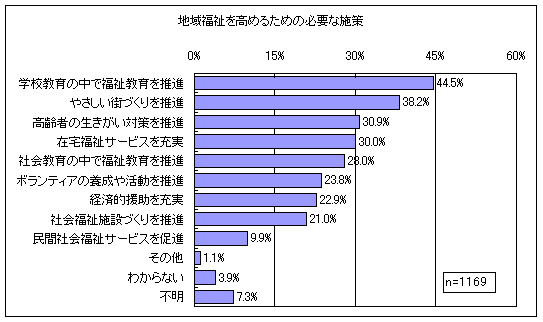
このうち「学校教育の中で福祉教育を推進する」は年齢の若い人ほど、居住年数の短い人ほど回答比率が高くなっている。また「やさしい街づくりを推進する」も年齢の若い人ほど回答比率が高くなっており、女性の回答比率も高い。「高齢者の生きがい対策を推進する」は男性の回答比率が高く、年齢が高くなるにしたがって回答比率も高くなっている。「社会教育の中で福祉教育を推進する」は30代の回答比率が高くなっている。
考察
地域福祉を高めるためには、施設・設備の整備やサービスの充実より、まず児童や成人を対象にした福祉教育によって住民の福祉意識を高めることが最も重要であると考えている人が多いことが分かる。平成6年の同様の調査では、第1位は「老人や障害のある人にやさしい街づくりを推進する」で40.9%、第2位は「学校教育の中で福祉教育を推進する」で34.8%、第3位は「保健・医療を充実させる」で33.8%、第4位は「老人などの生きがい対策を推進する」で21.5%となっていた。今回の調査と1位、2位が逆転している。
6-4.市民が福祉をよく理解するために
必要とされる方策
結果
市民が福祉をよく理解するために必要とされる方策について聞いたところ、1番多かった回答は「まちの広報などで、福祉情報の充実をはかる」で6割弱、第2位が「地域住民が、福祉施設の行事に参加しやすくする」で4割、第3位が「自治会活動や町内会活動の中に、福祉関連の活動を多く取り入れる」で4割弱、となっている。以下、「ボランティア活動への参加をうながす」「公民館などで行われる講座や学習会の中に、福祉関連の内容を多く取り入れる」が共に3割、「高齢者や障害者が、ボランティア活動に参画できるようにする」が3割弱、「福祉施設利用者が、祭りなどの地域行事に参加しやすくする」が2割強、「民間企業の社員教育の中に、福祉関連の活動を多く取り入れる」が2割となっている。このうち「福祉情報の充実をはかる」は、特に60歳以上の人からの回答に多くなっており、「地域住民が福祉施設の行事に参加する」は50代、60代前半の人からの回答に多くなっている。また、「自治会活動や町内会活動の中に福祉関連活動を」は60代前半の人、居住年数が5~10年未満の人からの回答に、「ボランティア活動への参加をうながす」は女性、前期ニュータウンの人からの回答にそれぞれ多くなっている。
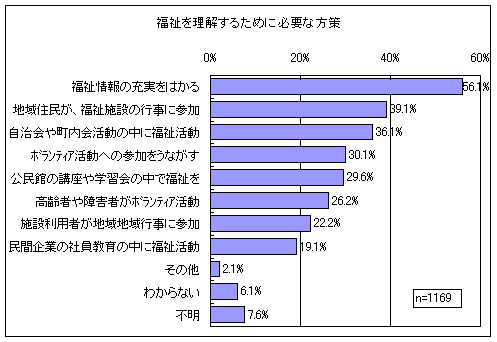
考察
以上から「福祉情報の充実をはかる」に回答数が多く、市民が福祉に関する情報を求めているということがいえる。それ以外では、ボランティアや施設行事など住民が福祉活動に実際に参加することによって理解が深まるといった、住民の参加をうながす様なことを推進していくべきだと思っている人も多い。また、自治会活動・町内会活動、公民館活動、企業の社員研修など、これまで福祉活動としてはあまり取り組みの進んでいない分野における活動の中にも手を広げることによって理解が進むと思っている人も多い。このように地域活動のあらゆる場に市民が参加しやすい条件を作ることが市民の福祉理解のために必要であると考えている。したがって、行政や関係団体、民間企業、当事者それぞれがそれぞれの立場で住民の福祉理解のための条件整備を図ることが必要となる。
6-5.社会福祉協議会および
ボランティア連絡協議会の認知度
結果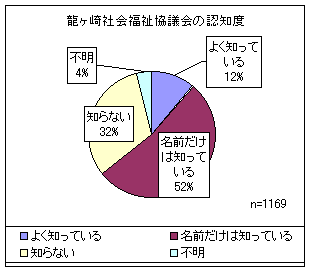
龍ケ崎市社会福祉協議会(以下社協)の認知度は、「よく知っている」または「名前だけは知っている」という回答は6割強となっているが、「よく知っている」という回答は1割強にとどまった。対象地区別では旧市街地が7割強と最も認知度が高く、性別では女性の方が認知度が高い。年齢別では40歳以上が7割を越えており、居住年数別では5年以上住んでいる人の認知度が6割を越えている。社協を「知らない」という回答は、佐貫地区と後期ニュータウンの2つの地区で4割近くにのぼる。これは、この2つの地区に居住年数が5年未満の人が多いことが、また、20代の人の6割弱が「知らない」と回答していることは若い人には社協を知る必要性があまりないことが理由として考えられる。
次に、社協が行っている事業の認知度については事業によって大きな差異がみられた。「ふれあい相談」が42.4%と最も高く、次いで「宅配給食サービス事業」が41.9%となっている。しかし、「餅つき広場」は7.8%と最も低い結果となった。性別では、「宅配給食サービス事業」が女性の方が1割以上も認知度が高い。「ふれあい相談」では30代は認知度が5割以上であるのに対し、「シルバーカー購入助成事業」では65歳以上が非常に高い。全体的に社協の認知度に比べ、事業を知っているという回答が多いのは、事業自体は知っていてもそれが社協の事業とは知らないで回答している人がいるからではないだろうか。
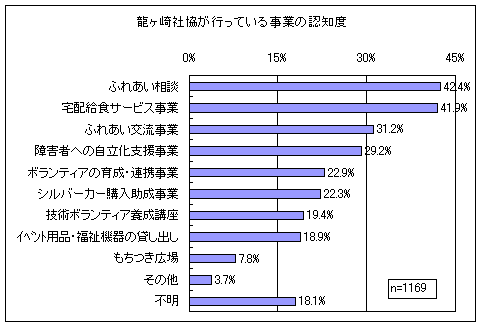
社協の福祉サービス利用経験の有無では、「ある」という回答が5%、「ない」という回答が85.2%であった。年齢別の「ある」という回答では20代が最も低く0.6%、60代前半が最も高く10.5%となっている。対象地区では居住年数の長い旧市街地区が最も高く、また、居住年数の短い後期ニュータウンが最も低いという結果になっている。.以上のことから、若者の利用や居住年数の短い人の利用が低いといえる。
龍ケ崎市ボランティア連絡協議会の認知度は「知っている」が6.8%、「名前だけは知っている」が24.0%、「知らない」が64.8%となっている。対象地区別では、旧市街地区で「知っている」という回答が多く、年齢別では、年齢が増すほど、「知っている」と回答した人が多い。居住年数では、居住年数が20年以上、生まれてからずっと住んでいる人は、知っていると回答した人が多い。
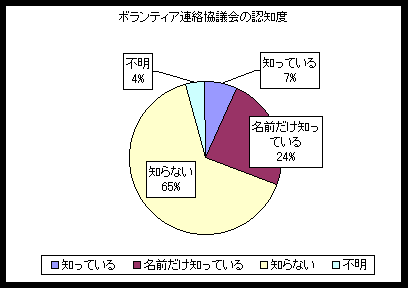
考察
以上の事から社協の認知度については、その大半が「名前だけは知っている」であり、その事業を知っている人は少なかった。これは、平成6年度の調査とほぼ同じ結果である。実際に対象者になる等、社協と関わりを持つ機会がなければ分からないようである。そのため福祉サービス利用経験の有無で「ある」という回答が少ないものと考えられる。また、社協は会員制になっており、会員の会費も活動資金の一部としている団体である。実際、会員になっている世帯は多いのだが、ほとんどの人は社協の会員であることを自覚していないものと考えられる。社協がどのような活動をしているかは知らないという回答も多かった。社協の認知度を高めるためには、社協の広報方法の改善はもちろん、地域住民が会員としての自覚を持つことやいろいろな活動に参加することによって、福祉の理解が深まり、社協の認知度も深まっていくのではないだろうか。
龍ケ崎市ボランティア連絡協議会に関して、全体では、認知度は低く、知られていないのが現状である。実際、生まれたときからずっと住んでいる人自体ボランティア連絡協議会を知らない(63.2%)ので、龍ケ崎市ボランティア連絡協議会のアピール・情報が少ないのではないだろうか。
6-6.市の福祉課題や生活課題に対する
回答者の関わり方
結果
龍ケ崎市においても今後進むと思われる高齢化や障害者、児童に関する事など多様化する福祉。そのような中で、あなた自身どのような関わり方をしたいと思いますか。という問に対し、「ボランティアには関心があるが、どんなことをどんな場所で、どんな風にできるのか内容等知りたいのに『入口』がわからない。」「余暇があまりなく、実際活動できない状況である。少しの時間でも出来る様な活動に参加していきたい。」等、ボランティアに関する意見が最も多い。「ボランティア活動に参加したい」が、実際に行動に移すとなると、「時間がない、情報が足りない」等の理由によって、足踏み状態であるのが現状のようである。逆に、自分から積極的に参加したくないという意見もみられた。
龍ケ崎市の行政に対しての意見も多く、その例としては、「もっと何らかの方法で、広報をする必要があるのではないでしょうか。」「市が中心になってきめ細かな福祉サービスの情報を流すべきだと思う。」というものがあった。福祉などの情報が少ないため、もっと情報がほしいと思っている人が多いようである。障害者、高齢者等がもっと住みやすい環境を作って欲しいという意見もみられた。
考察
これらの事から、福祉、特にボランティアに対する意識は高いものの、さまざまな理由から参加するには至っていない人が多いと考えられる。また、行政のバックアップを望む声も多い。住民と行政が良く話し合い、相互理解を深め、手を取り合って歩んでいく事が必要であると思う。それが、よりよい街づくりにつながるのではないだろうか。