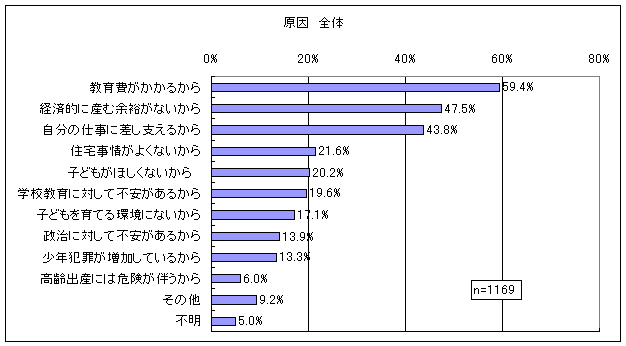
龍ヶ崎市における地域住民の
福祉意識に関する調査
Ⅳ-2.児童に関する住民意識 |
2-1.少子化問題について
近年、日本では高齢化率の伸びが著しく、まもなく4人に1人は高齢者という時代を迎える。しかし、これは単に65歳以上の老齢人口が増加しているというだけでなく、15歳未満の年少人口の伸び率が低下し、少子化が同時に進んでいることを意味している。そこで私たちは、「少子化の原因はどのようなことにあると思うか」、「少子化対策としてどのようなものが必要か」、「少子化が私たちの生活にどのような影響を与えると思うか」という質問を設定し、龍ヶ崎市民はどのように考えているのかについて知りたいと思った。その結果は以下のとおりである。
少子化の原因については、全体では、「教育費がかかるから」が59.4%で最も多く、次いで「経済的に産む余裕がないから」が47.5%、「自分の仕事に差し支えるから」が43.8%と続いている。
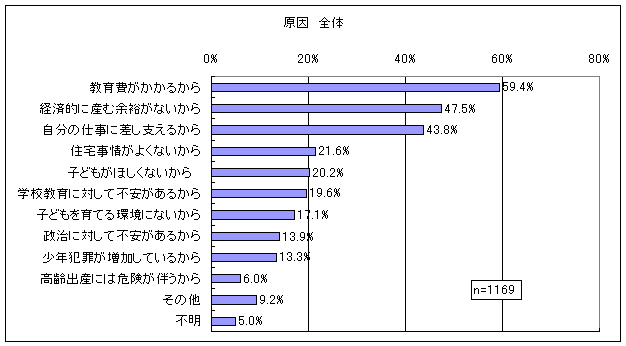
性別でみると、回答率で男性が女性を上回っている項目は「子どもがほしくないから」の25.3%のみで、その他の項目はすべて女性が男性を上回っていた。具体的には、「教育費がかかるから」が62.6%、「自分の仕事に差し支えるから」が48.7%、「学校教育に対して不安があるから」が22.5%、「少年犯罪が増加しているから」が15.4%となっていた。
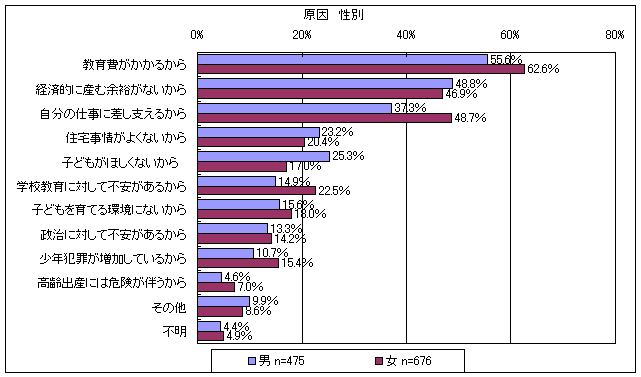
少子化対策として必要だと考えられているものについては、全体では、「教育費の軽減」が62.8%で最も多く、次いで「保育所の充実」が54.1%、「子育てに理解ある職場環境の整備」が46.9%、「子どもを預かる公的施設の整備」が44.6%、「ゆとりのある教育の実現」が43.5%と続いている。
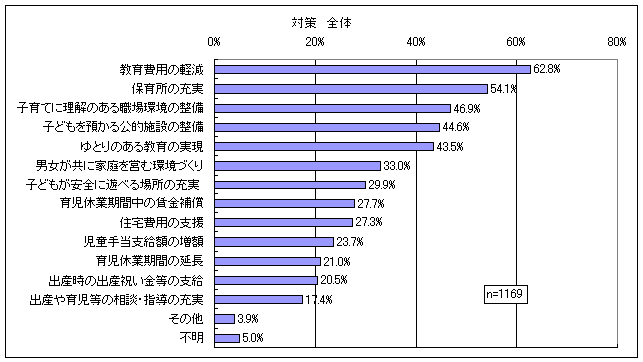
性別でみると、回答率で女性が男性を上回る項目が多く、「保育所の充実」が60.5%、「子どもを預かる公的施設の整備」が53.1%、「子育てに理解ある職場環境の整備」が50.7%、「出産や育児等の相談・指導の充実」が21.4%と続いている。また、年齢別にみると、20~39歳では「子育てに理解のある職場環境の整備」が61.8%、「児童手当支給額の増額」が37.6%、「育児休業期間の延長」が31.8%と回答率が高いのに対して、65歳以上ではそれぞれ28.1%、18.0%、16.4%と回答率に大きな開きが見られた。
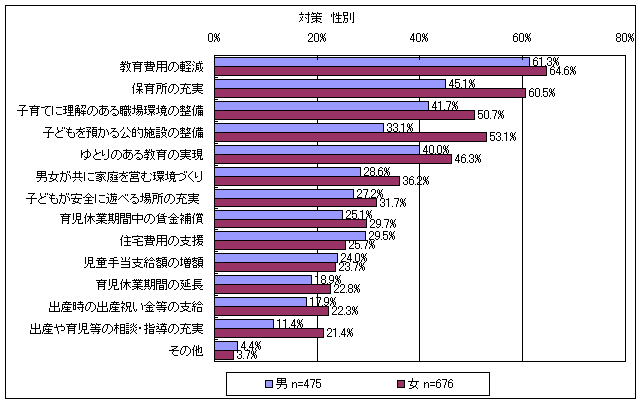
少子化が私たちの生活に与える影響については、全体では、「現役世代の負担の増加」が78.9%で最も多く、次いで「労働力人口が減少」が53.8%、「過疎化、高齢化など地域社会の変化」が48.6%と続いている。
性別でみると、回答率で男性が女性を大きく上回る項目が多く、「労働力人口が減少」が62.9%、「過疎化、高齢化など地域社会の変化」が51.6%、「人口の減少」が41.9%、「労働者人口の年齢構成の変化」が40.8%となっていた。
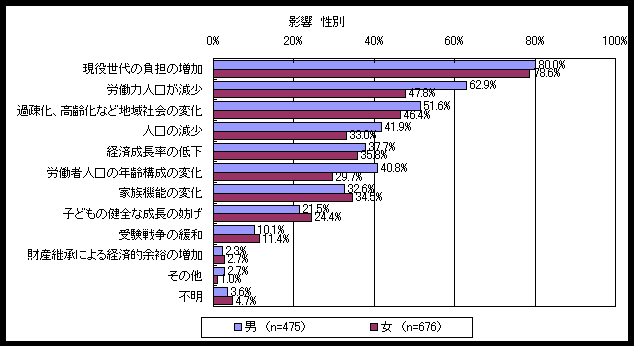
以上から少子化については、特に男女間での考え方に大きな差があることがわかる。男性は仕事や社会に関する項目への回答率が高く、女性は子どもに関する項目への回答率が高い。これは「男性は仕事、女性は家庭」という考え方が、未だに根強く残っている結果である思われる。また「自分の仕事に差し支えるから」という項目で女性の方が高い割合を占めているのは、出産や育児の女性にかかる負担が多いための結果と思われる。
2-2.保育について
わが国の少子化の背景としては、様々なことが考えられるが、核家族化の進行、女性の高学歴化、自己顕示意欲の高まりなどによる女性の社会進出の増大の中で、子育てと仕事の両立の難しさ、育児に対する心理的・肉体的不安、子どもの教育問題、経済的負担、住宅事情、固定的な夫婦役割意識など多くの要因が指摘されている。このような社会的な変化の中で、住民の子育てに対する意識が変化しているのか、その考え方や実態を明らかにするために、「日中誰が子どもの面倒をみた方が良いのか」、「子どもを保育所に預けることをどう思っているか」、「保育所の利用が良いと思う理由、良くないと思う理由」、「子育てをする上で子育てに対する知識をどこから得ているのか」のそれぞれを龍ヶ崎市民はどのように考えているかを知るべく質問を設定した。その結果は以下のとおりである。
日中における望ましい子育て担当者について、全体では、「父親・母親」が81.9%でそのほとんどを占め、「保育所」と答えた割合は6.6%であった。
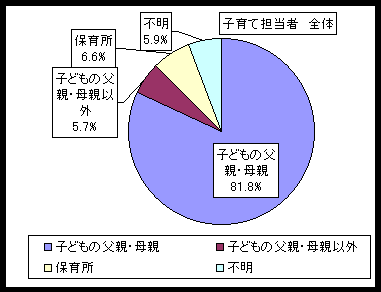
年齢別にみると「父親・母親」と答えた割合が30~39歳が87.4%と最も多く、20歳代・40歳代でも8割を超えていた。
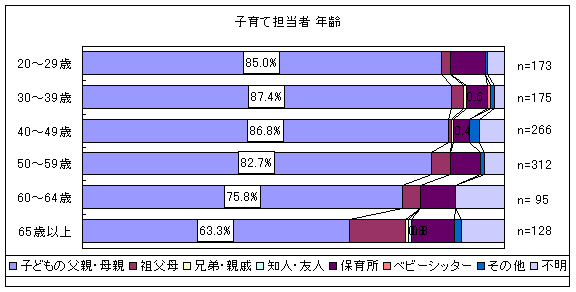
保育所に子どもを預けることの良否について全体では、「良い」と「どちらかというと良い」の合計である『よい』が65.6%、「どちらかというと良くない」と「良くない」の合計である『よくない』が26.4%と6割以上が保育所の利用についてよいと思っているようである。地区別にみると農業地区では72.5%の人が『よい』としているのに対し、最も低い前期ニュータウンでも60.8%と半数を超えている。
保育所の利用について『よい』とするものにその理由を聞いたところ、「集団行動が身につくから」が66.6%と最も多く、次いで「仕事を続けられるから」が59.1%、「子ども同士の交流が深まるから」が57.5%と続いている。年齢別にみると、20・30歳代では「集団行動が身につくから」、「子ども同士の交流が深まるから」が7割近くと高くなっており、40歳代と60~64歳では、多くの項目においてそれぞれ低い割合となっている。これは、保育を身近に感じている20・30歳代では、少子化が進んでいるために子どもが減り、子ども同士の交流が少なくなり、集団行動を身につけるための場がなくなっていると心配する人が多いため、他に比べて高い割合となったものと思われる。また、65歳以上では「しつけが身につくから」が27.9%、「家事に時間がとれるから」が25.0%で、他の年代よりも高い割合を示している。
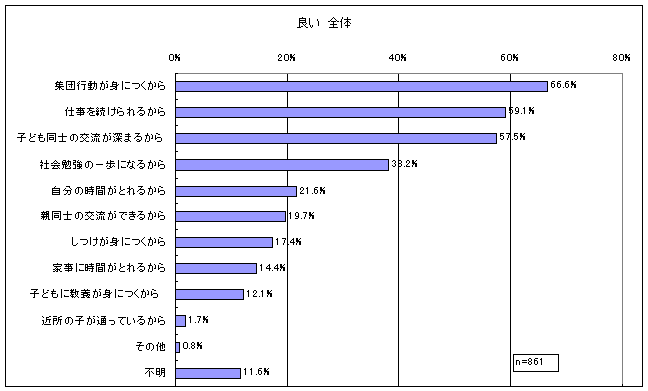
一方で、保育所の利用が良くないと思う理由について全体でみると「コミュニケーションが取れなくなる」と答えた人は62.9%と最も多く、ついで「費用が高いから」が15.7%と続いている。これは、少子化の影響により、一人の子どもに十分な時間を費やすことができるようになり、親と子のコミュニケーションの重要性や、家庭で育児を行うべきといった家族の絆を重んじている人が多いからだと思われる。
性別では、「コミュニケーションがとれなくなるから」と答えた人の割合は男性の方が女性より15%ほど多く、一方で、「保育所が必要ないから」と答えた人の割合は女性の方が男性より2倍近く多い。また、男性に比べて女性の方が「保育所の方針が合わないから」、「費用が高いから」、「いじめがあるから」と考えている人が多かった。これは、母親の方が、自分で子どもを守り育てようという意志が強く、その分保育所に対して信頼感や預けやすさを求めているのではないかと思われる。
年齢別にみると、20~29歳では「コミュニケーションがとれなくなるから」と回答した割合が76.1%とすべての年代の中で最も多くなっている。これは若い世代に子どもとのコミュニケーションの時間を多く持ちたいと考えている人が多いためだと考えられる。30~39歳では「保育所を利用する必要がないから」と回答した割合が他の年代よりも多くなっている。これは、子供が成長するまで自分で世話をしようと考えている人が多いためだと考えられる。
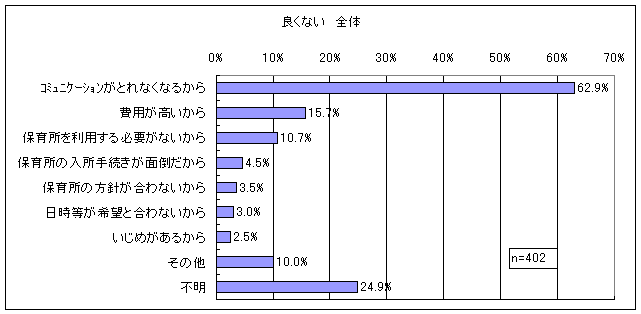
子育ての情報源については、全体では「自分の両親」と答えた人が76.0%で最も多く、次いで「知人・友人」が56.3%、「学校(幼稚園・保育施設等)」が27.4%と続いている。これはマスメディアから情報を得るよりも、身近な人との情報交換をする人が多いためだと考えられる。
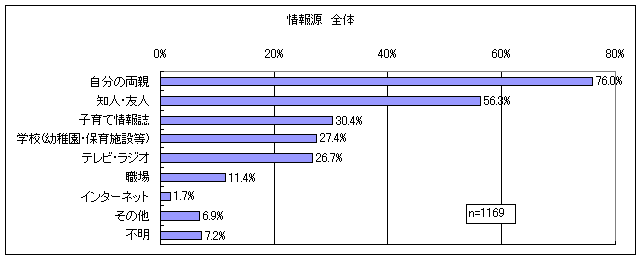
性別でみると、「子育て情報誌」からと答えた人が男性22.9%、女性36.1%、また「知人・友人」と答えた人は男性49.3%、女性61.7%とどちらも女性の方が多くなっている。このように、男女差から分析すると、女性は「子育て情報誌」、「知人・友人」といった、男性とは違った情報源から情報を得ている人が多いことがわかる。
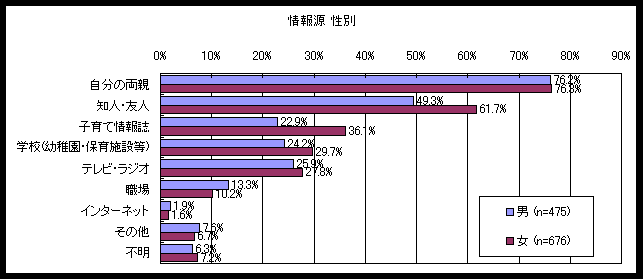
年齢別にみると、「自分の両親」という回答は、20~29歳が81.5%、30~39歳、50~59歳でも7割を超え、高い割合を示している。30~39歳でさまざまな項目において高い割合を示しているのは、現在子育てをしている人が多く、いろいろな情報を得ようとしている人が多いためだと思われる。65歳以上において「子育て情報誌」、「知人・友人」、「自分の両親」の割合が低いのは、小さな頃からきょうだいの世話などで、子育てを体験しているためだと思われる。
以上のような結果となったが龍ヶ崎市民の子育てに対する意識に関しては、日中、子どもの面倒をみるのは子どもの父親・母親がよいとするものがほとんどを占め、やはり子どもの面倒をみるのは、親であるべきという人が多い。
2-3.児童虐待について
結果
最近マスメディアなどで、子どもに対する虐待が注目されている。虐待とは、子どもが親、または保護者・養育者、時にはその他の大人により、子どもの健やかな成長・発達を損なうような暴行が加えられたり、または養育の拒否・怠慢等により適切な保護(日常的な世話や医療)が与えられなかったことをいう。
そこで私たちは、龍ヶ崎市民が「虐待に対してどのくらい関心を持っているのか」、「どのような行為を虐待と思うか」、「虐待が起こる原因はなにか」という質問を設定し、龍ヶ崎市民はどのように考えているのかを知りたいと思った。結果は以下のとおりである。
児童虐待に対する関心については、全体では、「非常に関心がある」と「どちらかというと関心がある」の合計である『関心がある』と答えた割合は83.9%、「どちらかというと関心がない」と「まったく関心がない」の合計である『関心がない』と答えた割合が11.0%と、市民の約8割が児童虐待について関心を持っていることが分かった。年齢別にみると、20歳代~50歳代では「どちらかというと関心がある」と回答した割合が多かったのに対し、60歳以上では「非常に関心がある」と回答した割合が多かった。
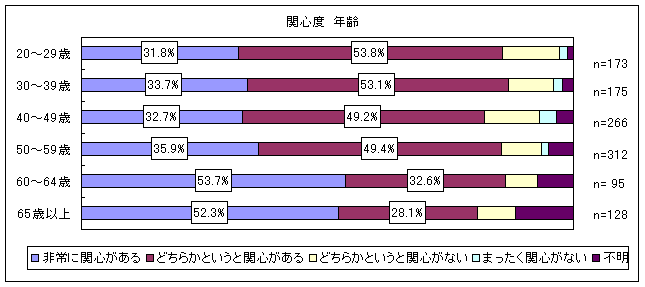
虐待と思う具体的行為については、全体では、「食事を与えない」が85.7%で最も多く、次いで「物を投げつける」が72.3%、「物を使ってたたく」が71.3%と続いている。
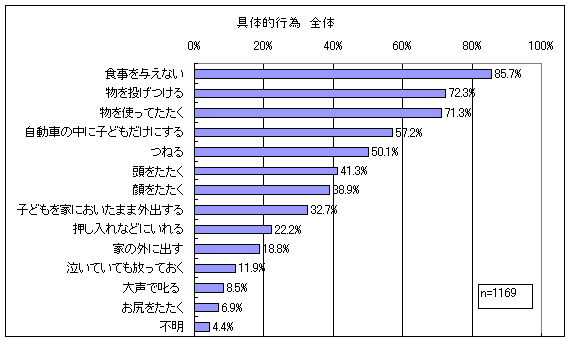
虐待が起こる原因についてみると、全体では、「夫やパートナーとの不仲」が41.3%で最も多く、次いで「育児についての相談相手がいない」が32.7%、「子供のしつけがうまくいかない」が26.1%、「パートナーが育児に協力してくれない」が25.2%と続いている。 年齢別にみると、20~29歳では「育児についての相談相手がいない」が38.2%と最も多く、次いで「夫やパートナーとの不仲」が33.5%となっており、60~64歳とともに「夫やパートナーとの不仲」について、回答率が他の年齢層に比べて低かった。 一方で、30歳代、40歳代、50歳代では「夫やパートナーとの不仲」を虐待の原因にあげる割合が多く、次いで「育児についての相談相手がいない」の順になっていた。
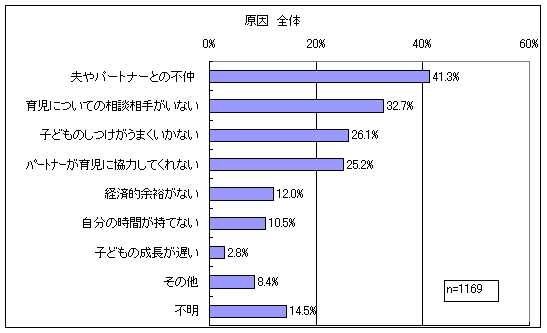
考察
虐待では、関心度について年齢別にみると、現在子育てをしていると思われる20歳~59歳においては、自分の子育てに一生懸命で、他人に目をむけている余裕がない為、「どちらかというと関心がある」の割合が「非常に関心がある」よりも高いと思われる。また、60歳~65歳以上の人は、子育てから離れ、核家族が進み、孫と離れて過ごす年配の人が多く、自分の孫の事の様にとらえてしまう為に「非常に関心がある」に高い割合を示したのだと思われる。
原因について、年齢別にみると、20歳~29歳の人が「夫やパートナーとの不仲」という項目について他よりも割合が低いのは、晩婚化が進み、未婚の人が多くいる為ではないかと思われる。次に子どもを育てている20歳~49歳の人は現在3世代家族や近隣の付き合いの減少により相談相手が少ないことや、自分の時間が持てないなど、育児によるストレスが虐待につながっているのだと考えられる。 性別でみると、男性は仕事などのストレス、女性は子どもと一緒にいる時間が多く、また育児についての相談相手がいないなどのストレスが、虐待につながってしまうのではないかと思われる。