結果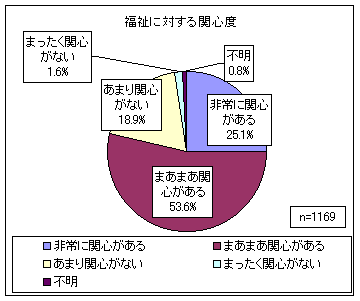
龍ヶ崎市における地域住民の
福祉意識に関する調査
Ⅳ-4.高齢者に関する住民意識 |
4-1.福祉への関心度
結果
社会福祉に「非常に関心がある」人は25.1%、「まあまあ関心がある」人は53.6%で、全体でみると8割を占めることから、龍ケ崎市民の社会福祉に対する関心は高いといえる。年齢別では、年齢が高くなるにつれて関心があると回答している人が多くなっている。
また、社会福祉でどの分野に関心があるかと聞いたところ、「高齢者に関すること」が62.3%と最も多く、「保健・医療に関すること」が43.9%とこの2つに集中している。以下、「地域福祉に関すること」「児童・青少年に関すること」「障害者に関すること」と続き、いずれも2割前後となっている。それに比べて「貧困・低所得者に関すること」「母子・父子家に関すること」は非常に関心が薄くなっている。
「高齢者に関すること」は年齢が高い人や居住年数が長い人ほど高くなっており、「児童・青少年に関すること」は後期ニュータウン地区、年齢が若い人や居住年数が短い人ほど高くなっている。「障害者に関すること」は年齢が若い人ほど高くなっている。また、社会福祉に非常に関心がある人は、「高齢者に関すること」「障害者に関すること」に、まあまあ関心がある人は、「児童・青少年に関すること」「保健・医療に関すること」に関心を持っていた。
考察
福祉への関心度では、自分または家族が実際に福祉サービスを利用する機会が増えたり、社会福祉に接する機会が多くなり、社会福祉を身近な問題としてとらえる人が多くなるため、社会福祉に「関心がある」と回答した人の割合も高くなっているものと思われる。また、平成6年の調査でも8割近くが「関心がある」と回答しており、今回の調査とあまり差異は見られない。
関心の対象では、「高齢者に関すること」に関心が高い。これは、急速な高齢化、介護保険制度のスタートによって社会的に取り上げられ、身近な問題として考えられるようになったためであると思われる。また、「保健・医療に関すること」に関心が高いのは、日常生活に密着している分野であるためであると思われる。「児童・青少年に関すること」に関心がある人は、年齢が比較的若く、居住年数の短いニュータウン地区の人で、この世代は子供をかかえる世代でもある。
4-2.老後に対する不安結果
「老後にどのような不安を感じていますか」という質問に対して「年金や生活費などの経済面」が53.4%ともっとも多く、「体力の衰えや健康面」が35.2%、「健康を害したときの介護者、世話人の面」が32.8%、「病院などの医療施設の充実の程度」が17.6%といった順に多くなっている。「老人福祉施設の充実の程度」9.7%、「趣味や社会生活などの生きがい」6.6%、「退職後の就労」5.4%、「隣近所や地域の人との付き合い」1.5%とこれらに不安を持っている人は少ない。
「経済面」については、後期ニュータウン、男性、年齢が若い人ほど、居住年数が短い人ほど不安に思っている人が多く、「健康面」については、年齢が高くなるほど多くなっており、「介護者・世話人」については、女性で多くなっている。
考察
以上のように、老後の不安については、「年金や生活費などの経済面」に不安を持っている人が最も多く、全体の約5割を占めている。これは、自分が老後になった時、どの程度の暮らしが出来るかは、経済面がもっとも重要になってくるからだと思われる。次いで「体力の衰えや健康面」「健康を害した時の介護者、世話人」となっているが、「隣近所や地域の人との付き合い」や「退職後の就労」・「趣味や社会活動などの生きがい」などの日常生活に対して不安を感じている人は少ない。
なお、経済面の不安に対しては、年齢が若い人ほど、不安が多くなっているのは、老後までの期間が長いという事から経済設計をたてにくいことにより、不安が高まる為だと考えられる。また、その時期に果たして年金の支給が受けられるのか、といった不安もあるものと思われる。女性に「介護者・世話人の面」に対する不安が多いのは、平均寿命が女性の方が長いため、自分に介護が必要になった時、配偶者はすでに他界しているケースが多いと考えられるため、配偶者には期待できないと思っているからではないか。平成6年の調査では「健康面」が45.3%、「経済面」が36.0%となっていた。今回の調査では「経済面」が53.4%、「健康面」35.2%と、前回の調査結果と比較すると大きく変化している。この変化は現在の不況や介護保険制度による保険料の徴収などが関わってきていると考えられ、健康面よりも経済面の不安の方が大きくなったものと思われる。
4-3.近所の高齢者が手助けを必要としたときの対応結果
「もしあなたの近くの一人暮らしの高齢者が、万一病気などで寝込み何らかの手助けが必要になった場合、まずどうしますか」という設問に対し、全体では「近所の人と相談し、みんなで協力して手助けする」が22.6%、「自分でできることを探して手助けする」が18.9%、「市役所に連絡する」が15.4%、「地域の民生委員に連絡する」が14.7%、「近所の人から話があれば協力する」が13.6%、「何もできないと思う」が7.6%となっている。
「近所の人と協力して手助けする」と回答した人は、後期ニュータウン、50~64歳、家族の中に高齢者のいる人に多くなっている。「できることを探して手助けする」と回答した人は、後期ニュータウン、女性、家族の中に高齢者のいる人に多くなっている。また、「近所の人から話があれば協力する」と回答した人は、農業地区、年齢が若くなるほど、「地域の民生委員に連絡する」という人は、佐貫地区、女性、家族に高齢者のいる人、年齢が高くなるほど、「何もできないと思う」人は、年齢が若くなるほど多くなっている。
考察
以上から、近所の高齢者が手助けを必要となった時の対応としては、「近所の人と協力して手助けをする」や「できることを探して手助けする」というように、主体的に高齢者と関わって対応しようとしている人が多い。これは、居住年数の比較的長い農業地区よりも、居住年数の短い後期ニュータウン地区の人に多くなっていることに注目できる。農業地区の人や若い年代は、「近所の人に話があれば協力する」といった、どちらかといえば受動的な関わりをしようとしている人が多い。また、自らは直接関わらず市役所や民生委員に連絡するといった間接的な対応をしようとする人は、家族の中に高齢者がいる人の方がいない人に比べ比率が高いというのは、いかなる理由なのか。
4-4.あなた自身が要介護者になった場合の希望する介護者
結果
「自分自身が高齢になり介護が必要になったとき、誰に介護してもらいたいか」という設問に対して、全体では、「配偶者」という回答が45.9%と約半数を占めており、次いで、「施設に入所する」という回答が24.4%と高くなっていた。以下、「娘」「ホームヘルパー」「嫁」という順であった。「配偶者」では、男性、前期・後期ニュータウン、「施設に入所する」では、女性、前期ニュータウン、居住年数が長い人ほど、「娘」では、女性、旧市街地、「嫁」では、65歳以上の人が多くなっている。
考察
以上の中で特に注目したいのは、男女間による回答傾向の違いである。男性は老後の介護を配偶者にまったく依存しきっている。これに対し女性は配偶者に期待している人は男性の半分近くであり、「施設入所」「娘」というように分散している。これは、男性は、介護を家事労働、育児と同等に考え、女性の役割と思っていることと、夫が年上という夫婦が多いことに加え、女性の平均寿命が男性より長く、夫は妻による介護を受けやすい立場にあるため、配偶者による介護を望む男性が女性より多くなっていると考えられる。一方、女性は平均寿命が長いため、夫にあまり期待できないと考え、施設入所や娘に期待しているのではないかと思われる。また、これまで、主たる介護者は「嫁」である場合が圧倒的に多いが、介護希望では2%とわずかであることに注目される。
4-5.両親や配偶者が要介護者になった場合の介護結果
あなたの両親や配偶者等が、高齢のため介護が必要になった時どうしますかという設問に対し「各種の在宅福祉サービスの利用を中心に考え、不足分を家族で介護する」が 52.3%と最も多く、次いで「福祉サービスの利用はあまり考えず、家族による介護を中心に考えていく」が26.6%となっている。これは、在宅介護を基本に考えている人が多い事がわかる。それに対し「家族による介護が難しいため、施設に入所してもらう」は8.0%と少ない。
「在宅福祉サービスを中心に介護」と回答した人は、地区別では、後期ニュータウン、佐貫地区で多く、性別では女性、年齢では30代・40代、居住年数では10年未満の人に多くなっている。反対に「家族による介護中心に」と考えている人は、地区別では農業地区、性別は男性、年齢では20代、居住年数では10年以上・生まれた時からずっと住んでいる人に多くなっている。また、「施設に入所してもらう」は65歳以上の人、居住年数が20年以上の人で1割を超えている。
考察
この様に、両親や配偶者の介護は福祉サービスの利用を中心に考えている人が多く、特に介護の主たる担い手である女性、居住年数の短いニュータウンの人はその様に考えている人が多い。しかし居住年数の長い農業地区の人などは、従来の家族の介護は家族でするものという考えが依然として残っているものと思われる。平成6年の調査では、家族での介護を考えている人が全体の7割を占める。また在宅福祉サービスを活用したいと考えている人は1割にも満たず、今回の調査と全く違う結果となっていた。これは、この6年間で介護についての意識が大きく変わってきたことの現われである。介護保険の導入が、これまでの家族中心の介護から、在宅福祉サービス中心の介護に変えたものと思われる。6年前と比べ福祉サービスを利用することに抵抗が無くなったり、保険料を支払うことにより、福祉サービスを利用することが当然の権利として考えるようになったためと思われる。