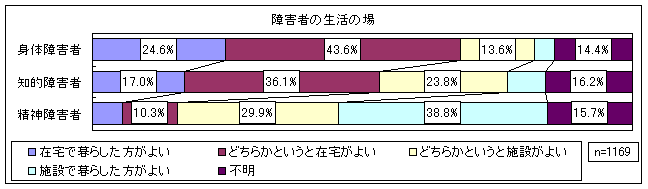
龍ヶ崎市における地域住民の
福祉意識に関する調査
Ⅳ-3.障害者に関する住民意識 |
3-1.障害者の生活の場
結果
(1)身体障害者
「身体障害者の生活の場は在宅か施設のどちらがよいと思いますか」という設問に対して、「在宅で暮らした方がよい」という回答は24.6%、「どちらかというと在宅で暮らした方がよい」という回答は43.6%、これを合わせた「在宅」と回答した人が68.2%と約7割を占めている。これに対し、「施設で暮らした方がよい」という回答は3.8%、「どちらかというと施設で暮らした方がよい」という回答は13.6%、これを合わせた「施設」と回答した人は17.4%と少なかった。
「在宅」については、男性、後期ニュータウン、居住年数が短い人、年齢が若い人ほど在宅で暮らした方がよいと回答しており、「施設」については女性、農業地区、居住年数が長い人、年齢が高くなるほど多くなっている。
(2)知的障害者
「知的障害者の生活の場は在宅か施設のどちらがよいと思いますか」という設問に対して、「在宅で暮らした方がよい」という回答が、17.0%、「どちらかというと在宅で暮らした方がよい」という回答は36.1%と、これを合わせた「在宅」と回答した人は53.1%と5割を超えている。「施設で暮らした方がよい」という回答は6.9%、「どちらかというと施設で暮らした方がよい」という回答は23.8%と、これを合わせた「施設」と回答した人が30.7%となっている。「在宅」という回答の方が、「施設」という回答よりも多い。
「在宅」については、女性、後期ニュータウン、居住年数が短い人、年齢が若い人ほど在宅で暮らした方がよいと回答しており、「施設」については女性、農業地区、居住年数が長い人、年齢が高くなるほど多くなっている。
(3)精神障害者
「精神障害者の生活の場は在宅か施設のどちらがよいと思いますか」という設問に対して、精神障害者の場合は「在宅で暮らした方がよい」という回答は5.5%、「どちらかというと在宅で暮らした方がよい」という回答が10.3%となっており、これを合わせた「在宅」と回答した人が15.8%と比率が低い。一方「施設で暮らした方がよい」という回答は38.8%、「どちらかというと施設で暮らした方がよい」という回答が29.9%で、これを合わせた「施設」と回答した人が68.7%となっており、圧倒的に「施設」が多くなっている。
「施設」については後期ニュータウン、男性、年齢は若い人ほど、居住年数は長い人ほど施設で暮らした方がよいと回答しており、「在宅」については、女性、農業地区、年齢が高い人、居住年数が短い人ほど多くなっている。
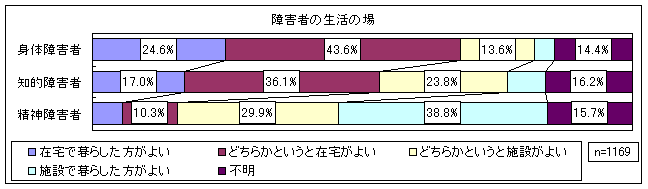
考察
私達がこの質問を考えた前提に、1980年代以降の福祉の動きを特徴づけるもの、いわゆる、「ノーマライゼーション」の理念が、龍ヶ崎市民にどの程度浸透しているか、地域によってその度合いはどれほど異なっているかを調べたかったことが挙げられる。今回の調査結果から、農業地区よりも、後期ニュータウンの方がこの理念は浸透しており、このことは身体障害者・知的障害者の回答に当てはまっている。
身体障害者・知的障害者の回答の割合が、「在宅」に集中しているのに対し、精神障害者は1割強とはるかに少ない数字となった。精神障害者の在宅の割合が少ない理由として「他人に危害を加える可能性が高い」「専門知識が必要になる」というものがあり、自分たちが面倒をみるのがつらいと言うよりも、人への影響に関する内容のものが多かった。
農業地区では望ましい障害者の場として「在宅」よりも「施設」で暮らす方がいいと答えた人が多かった。他の地域に比べ居住年数が長いこの地区では、固定的な観念を抱いている人が多く、障害者の抱える深刻な問題を解決する社会的な取り組みは、福祉施設や障害者施設で行うべきだと考える人達が多い。その反面、比較的新しい後期ニュータウンの住民は、障害者の生活の場として、「在宅」でと答えた人が約6割を占めた。障害者は特別視されるのではなく、社会の普通の生活条件、生活様式の中で生活するべきだとする意見や、家族と生活しているときが本人の精神的安堵感につながる1番の理解者は家族だとする意見だった。このようなノーマライゼーション理念が浸透している理由として考えられるのは、それまで都市で暮らしていた人達が、ニュータウンへと越してきたという背景が関係しているものと思われ、今回の調査でこのような結果が出たのではないか。
3-2.知的障害者施設建設に対する賛否
結果
自分の家の近くに知的障害者施設が建設されるとしたら賛成か、反対かを聞いたところ、「賛成」と回答した人が23.7%、「どちらかというと賛成」と回答した人が35.8%、「どちらかというと反対」と回答した人が20.4%、「反対」と回答した人が2.9%という結果になっている。6割の人が賛成と回答し、2割程度の人が反対と回答している。知的障害者という存在が複雑で不明という回答もあった。地区別では、後期ニュータウン地区、年齢別では20代と60代以上は賛成と回答した割合が高かった。
考察
半数以上の人は賛成と回答したが、一部では知的障害者の理解に対して個人差があり、家の近くに建設されることによって、現在の環境が変わるということに抵抗があるようだ。また、ゴミ処理場や墓地のように必要であると考えているが、自分の家の近くに出来ることは避けたいという声があった。また6年前の調査でも、7割近くが賛成、3割が反対とあまり差異は見られない。
3-3.障害者が充実した生活を送るための条件
結果
障害者が充実した生活を送るための要件として「働くための職業訓練や雇用促進対策を進める」が47.3%と一番多く、職業訓練や雇用促進を重視していることが分かる。続いて、「日常生活できるよう機能訓練をする」(42.8%)と、「公共施設や交通機関の整備」(40.1%)が、他に比べて比較的多い。以下、「障害者理解の教育の促進」36.0%続いて、福祉施設の整備の充実が20.7%在宅福祉サービスの充実が20.6%と続いている。
「職業訓練や雇用促進対策を進める」については、女性、後期ニュータウン、居住年数が5から10年未満、年齢が40~64歳の人の回答が高くなっており、「機能訓練をする」については、年齢が60代以上、居住年数が20年以上の人の回答が比較的高くなっており、「障害者理解の教育の促進」については、女性、後期ニュータウン、居住年数が5年未満、年齢が30代の人の回答比率が高くなっている。「公共施設や交通機関の整備」については、後期ニュータウン、女性、居住年数が5~20年、また年齢が20代の人の回答比率が高い。
考察
全般的な傾向として年齢の若い人は「公共施設や交通機関の整備」や「障害者理解の教育の促進」などに回答した人が多く、障害者が地域で生活していく上で、物理的な障壁や住民の障害者意識の改善が必要であると思っている人が多いようである。つまり、社会が障害をありのままに受け入れて共生していこうという考えがあるように思われる。これに対して、年齢の高い人は「日常生活ができるよう機能訓練をする」という回答が多くなっている。これは、障害者が地域で生活するためにはまず障害者自身が自らの障害を克服することが何よりも大事なことである、と考えている人が多いように思われる。「職業訓練や雇用促進対策を進める」という回答は、50代を中心とした中堅層の回答に多いが、これは障害者の社会参加を、制度を含め社会的責任で改善していかなければならないといった考えがあるようである。